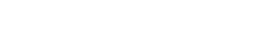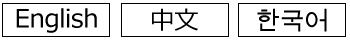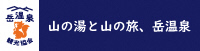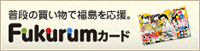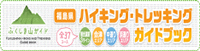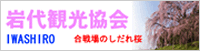戊辰戦争の中の二本松の戦いにおいて、藩の兵力は仙台などの応援兵を合わせても僅かに約1千人。
それに対して薩摩・長州・土佐などの西軍は、約7千人。
徹底抗戦の末、1868年(慶応4・明治元年)7月29日正午前、ついに二本松城は炎上し、落城しました。
落城・敗戦は誰もが予想し得たことでしたが、奥羽越列藩同盟の信義のために貫いた二本松藩の守信玉砕戦は、他藩には見られない壮絶な最期でした。
戦死・負傷者の数は記録によって違いがあり、1890(明治23)年に調製された、「戦死姓名簿」によると、二本松藩の戦死者337人、負傷者71人でした。
負傷者が少ないのは自分を恥じて届出をしなかったためともいわれ、また他藩の戦死者は200人を超えたといいます。
旧二本松藩主丹羽家菩提所の大隣寺境内には、戊辰戦争殉難者の戦死郡霊塔とともに、二本松少年隊隊長の木村銃太郎、副隊長の二階堂衛守と、少年隊戦死者14人の供養塔が建立されています。明治維新の夜明け前に、愛する郷土そして家族を守るために激戦の末に可憐な花を散らし、義に殉じた少年隊士を弔う参詣者の献花と香煙は今なおその悲劇を伝えています。
- 各古戦場での出来事
大壇口古戦場
供中口古戦場 - 二本松少年隊に関する項目
大隣寺
大手門(旧二本松城大手門)
霞ヶ城公園
二本松少年隊の命名
正式に編成され名が付けられた会津藩の少年16、17歳からなる「白虎隊」とは違って、二本松藩の場合は西軍(討幕軍)が二本松城下に切迫する直前に。出陣を志願した13歳~17歳までの少年たちが緊急に各部隊へ配属されたため、正式な名前はありませんでした。
1917年(大正6年)9月15日、戊辰戦争後「賊軍」の汚名をかぶされ、ひたすら沈黙を通し続けてきた旧二本松藩士により戊辰戦争戦没者の50回忌法要が、旧藩主丹羽家菩提所の大隣寺において盛大に行われました。
この時、二本松町の助役であり、戊辰戦争に木村銃太郎門下生として大壇口に14歳で出陣した水野好之(当時の名前は進)は、本文32ページほどの謄写版印刷した小冊子を作成し、参列者に配布しました。
表題は「二本松戊辰少年隊記」として、少年たちの服装や大壇口出陣の隊員名、激戦の様子などを回想記述したもので、この表題を基に、「二本松少年隊」と命名されました。
そして、少年隊に対する公然的な顕彰が行われるきっかけともなりました。
少年隊士の数
「二本松戊辰少年隊記」には、銃手として25人が列記されていますが、この数は、大壇口に出陣した隊長木村銃太郎門下生などに限られます。
うち、戦死者は隊長、副隊長及び隊士13人(大壇口古戦場戦死者1人を含む)、負傷者1人と記述されています。
1926年(昭和元年)に刊行された「二本松藩史」には、緊急によって確実な記録がないため、記載漏れや誤記があることを断った上で、51人が列記されています。また、戦死者は隊長と副隊長を除いて14人、負傷者は3人となっております。
その後、郷土史家平島郡三郎、青山正一、紺野庫治らにより、調査研究が進められて59人に増え、さらに1940年(昭和15年)には2人が追加され61人となりました。
その後も紺野の調査研究は続けられ、1981年(昭和56年)に刊行された「絵で見る二本松少年隊」では1人が追加されて62人となり、隊長と副隊長を除く戦死者のまま、負傷者は7人に増えています。
出陣許可と「入れ年」制度
1868年(慶応4年)5月1日、西軍が白河城を占拠、二本松藩兵の大半が西軍との白河城攻防に従事している間に、6月24日棚倉城落城。
一方、6月16日いわき平潟港に西軍別隊が上陸。→7月6日守山藩降伏→7月13日平城落城
このような戦況の中、同盟の三春藩による西軍への寝返りの噂もあって、二本松藩は領境の郡山・笹川・糠沢、そして小野新町に藩兵を派遣し警固にあたりました。
7月26日白河より進軍した板垣退助隊は三春城に無血入城、噂された三春藩の背信でした。
二本松領に急迫した西軍に対して、二本松城は空虚同然でした。
この城兵不足が少年たち、そして一度隠居した老人までも出陣するという原因にもなりました。
特に、出陣を嘆願する少年たちは「入れ年」制度という習慣を巧みに解釈したのです。
「入れ年」制度とは
二本松藩では成人としての扱いを受けるのは、数え年20歳でした。
しかし、18歳になった時点で藩に成人した旨の届け出をすると、藩は番入り(兵籍に入ること)を命じる習慣がありました。
つまり、2歳のさばを読むことを黙認することで、これを「入れ年」といい、二本松藩独特の制度でした。
7月上旬、藩は兵力不足のため17歳まで出陣を許可しました。
「入れ年」をあてはめると15歳までの少年が対象となるものの、藩の許可と部隊への配属がなければ出陣することはできませんでした。しかし、少年たちの出陣嘆願は日増しに多くなり、砲術指南木村銃太郎の門下生たちも全員で相談して、銃太郎に出陣許可の取りなしを何回となく懇願したといいます。


7月27日、本宮が占領されたことを受けて藩は15歳までを許可、「入れ年」にすると13歳までが対象となりました。兵力不足の実情と、2歳の差を黙認するという習慣がなだれ式に崩れ落ち、数々の悲劇を生む少年たちの出陣となったのでした。
出陣許可を得た少年たちの様子について、水野好之は前期の小冊子で、「七月二十六日の朝、俄然余等(がぜんよら)に出陣の命下る。余等の満足例うるに物なし。」と述べ、また15歳の木滝幸三郎は「二本松藩史」の中で「藩庁に対し数回嘆願せしに、二十七日に至り漸(ようや)く許可せられ雀躍して喜べり(こ踊りして喜ぶこと)。」と語っています。
出陣許可の伝達の仕方によるものか、記憶の誤りによるものか、26日説と27日説があります。
少年隊の出陣服装
「二本松戊辰少年隊記」によると、少年たちの服装は「上衣は呉呂(薄く柔らかく織った毛織物、また、メリンスの類)、または木綿の筒袖で、力紗羽織または陣羽織を着用。
下衣はダン袋、股引、義経袴、立附とまちまち。兵糧袋とに肩印。
帽子は用いず、白木綿の鉢巻、髪は髻(もとどり)を打糸で結んで背に下げた。
肩印は麻の布で長さ三寸(約9センチメートル)、巾一寸五分(約4.5センチメートル)くらいで、中央に違棒の紋を書き、鯨または竹を当て、中央を紐でくくり左肩先に結いた。」と記述されています。
おそらく多くの家庭では、母が徹夜で父や兄の着物などを少年の体に合わせて縫い、何とか形のみを整えただけのものであり、少年たちの服装はまちまちでした。
また、体が小さいために、刀を佐々木小次郎のように斜めに背負った少年や、刀を抜くときは他の少年に抜いてもらったり、あるいは二人が向かい合い腰を折って、互いに相手の刀を抜いた、と生存した少年らが伝えています。
武谷剛介の回顧談
藩のため戦争に出て戦うことは、武士の子として当然のことであって、特に語るべきことではない。恐ろしいとは思わなかった。
出陣の前夜などは、今の子どもの修学旅行の前夜のようなはしゃぎようだった。
出陣に際してのドラマ
少年たちの出陣に際して、それぞれの家庭でのドラマが語り伝えられています。
徳田鉄吉(13歳)
母・秀は「出陣の門出に、母の言うべきことではないが、当主の佐七郎(鉄吉の兄)が不在なので・・・」と、戦陣での心得を諭した後に、「徳田の家名を汚すことのないよう。」
また、亡くなった祖父や父の文まで忠勤を励むように。」と激励したと、後に語ったといいます。
上崎鉄蔵(16歳)
一時は大喜びしていたが、時がたつに連れて物思いに沈むようになり、これを見た母・スマはその訳を問いただしたところ、「恥ずかしくない刀を持って戦いたい」とのことでした。
上崎家には実戦用の両刀がなかったのです。
鉄蔵の気持ちを汲み取った母は、すぐに実家にかけつけて相州ものを調達し、鉄蔵に与えました。27日の朝、出陣する鉄蔵を母は祖母と共に見送り「行ってこいよ」と、いつものように声をかけると「行ってこいよ、ではないでしょう。今日は行けでいいのです。」と答えて玄関を出て、にっこり微笑み、ちょっと頭を下げると元気よく駆け足気味に立ち去ったといいます。
戊辰戦役50回忌にあたり、鉄蔵との最後の別れを語ったスマは、「言の葉の 耳に残るや 今朝の秋」と詠んでいます。
岡山篤次郎(13歳)
最初の木村銃太郎門下生です。母に頼んで戎衣(戦場での着物)をはじめ、手ぬぐいにいたるまで「二本松藩士 岡山篤次郎 十三歳」と書いてもらい出陣しました「母が屍を探すときにわかりやすいように。字が下手だと敵に笑われる。」との理由からだと伝えられています。
久保豊三郎(12歳)
母に何度も出陣を願ったものの、年が満たないため許されませんでしたそれでもねだるように出陣を求めたため、母は困り果て「幼いから、間近に砲声でも聞いたら恐ろしくなって帰ってくるだろう。」と考え、下男と一緒に行く事を許しました。
豊三郎は下男の手を引くようにして、大壇口に向かって行ったといいます。
兄の鉄次郎も大壇口に出陣しています。
成田才次郎(14歳)
父から「敵を見たら斬ってはならぬ。突け。ただ一筋に突け、わかったか。わかったら行け、突くのだぞ。」と、教え諭され出陣したといいます。
この突きは、初代藩主・丹羽光重公以来の二本松藩伝統の剣法です。
戊辰戦争出陣(二本松少年隊士)負傷・戦死者名簿
| 隊士名・年齢 | 出陣地・死傷 | 墓所 |
|---|---|---|
| 久保豊三郎(12歳) | 大壇口へ出陣。負傷。 | |
| 久保鉄次郎(15歳) | 大壇口へ出陣。負傷。 | |
| 高橋辰治(13歳) | 大壇口で戦死。 | 心安寺 |
| 遊佐辰弥(13歳) | 大壇口で戦死。 | 本久寺 |
| 徳田鉄吉(13歳) | 大壇口で戦死。 | 心安寺 |
| 大島七郎(13歳) | 大壇口へ出陣。負傷。 | |
| 岡山篤次郎(13歳) | 大壇口で戦死。 | 蓮華寺 |
| 小川安次郎(13歳) | 大壇口へ出陣。負傷 | |
| 成田才次郎(14歳) | 二本松城箕輪門近くで戦死。 | 大隣寺 |
| 木村丈太郎(14歳) | 大壇口で戦死。 | 心安寺 |
| 奥田午之助(15歳) | 大壇口で戦死。 | 台運寺 |
| 木滝幸三郎(15歳) | 他の戦場で負傷。 | |
| 三浦行蔵(16歳) | 大壇口で負傷。 | |
| 田中三治(16歳) | どのように戦死したかは不明。 | 顕法寺 |
| 根来梶之助(16歳) | 箕輪門前の脇の城壁直下近くで戦死。 | 台運寺 |
| 上崎鉄蔵(16歳) | どのように戦死したかは不明。 | 台運寺 |
| 岩本清次郎(17歳) | どのように戦死したかは不明。 | 蓮華寺 |
| 大桶勝十郎(17歳) | 大壇口で戦死。 | 善性寺 |
| 小沢幾弥(17歳) | 久保丁坂の中ほどで土佐兵と遭遇しましたが、精根尽き果てたためか介錯を頼み、その場で絶命。 「大手門」ページ内に詳細 |
法輪寺 |
| 中村久次郎(17歳) | どのように戦死したのかは不明。 | 台運寺 |
| 小川又市(17歳) | どこで戦っていたのかは不明。負傷。 |
大壇口出陣少年隊指揮者(共に戦死)
隊長 木村銃太郎(22歳)
大壇口で重傷を負い、副隊長に「この重傷では到底お城には帰れぬ。我が首を取れ」とお願いした。
墓所は正慶寺。
副隊長 二階堂衛守(33歳)
大隣寺前の参道で狙撃され即死。
墓所は大隣寺。
二本松少年隊に関してのお問い合わせ
二本松市教育委員会(二本松市役所内)
TEL:0243-55-5154